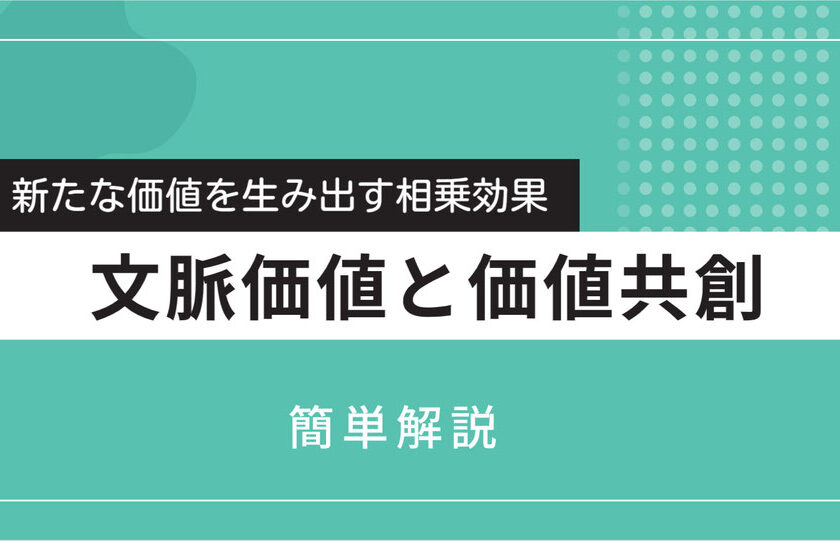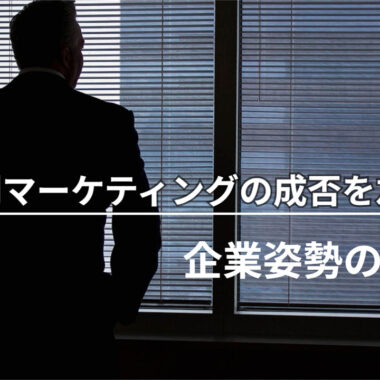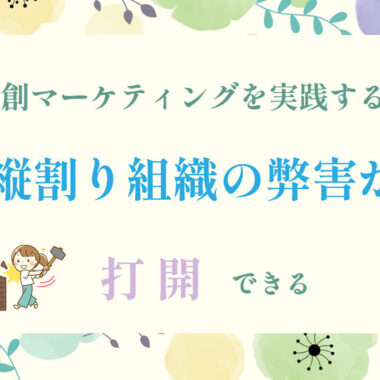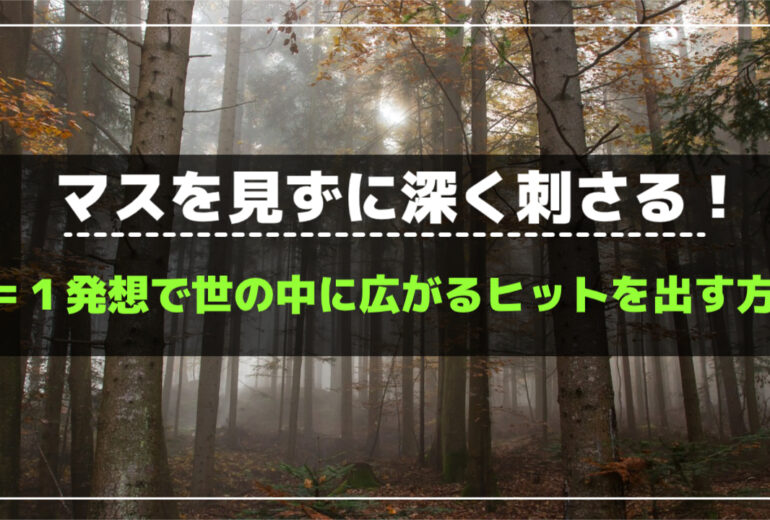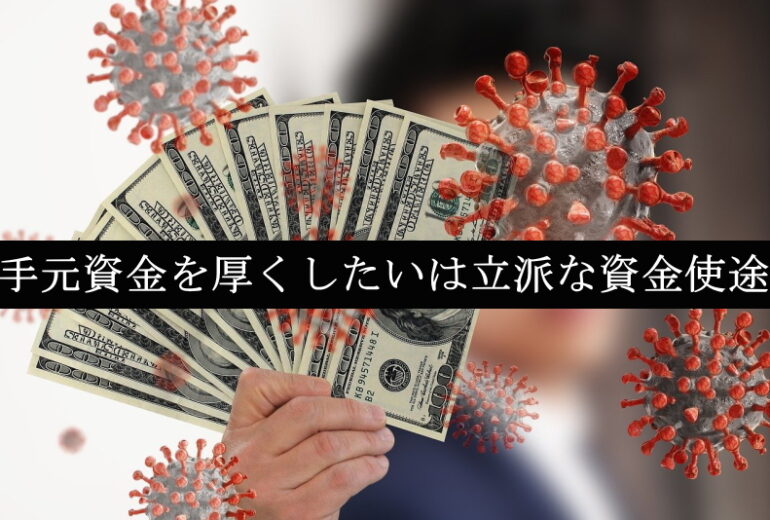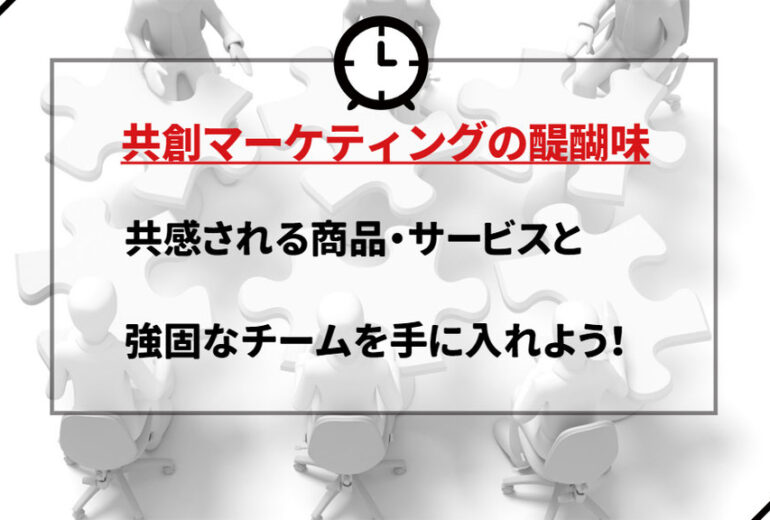文脈価値と価値共創
現在のように市場が成熟すると、流通している商品の多くが機能・性能等で類似し、メーカーごとの個性が失われ、商品を差別化・独自化することが困難になります。
その結果、消費者にとってはどのメーカーの商品を購入しても大差のない「コモディティ化」が進行してしまいます。
近年では 「企業は価値の提案者にすぎず、価値は顧客により創造される」 という考えが広がっており、これは サービス・ドミナント・ロジック(S-Dロジック) の影響を受けています。
サービス・ドミナント・ロジックと文脈価値
S-Dロジックでは「文脈価値」の重要性が強調されています。これは商品の価値が「使う場面・状況=文脈」に依存して決まるという考え方です。
Vargo & Lusch:「価値は個別的で、経験的で、文脈依存的で、意味内包的である」
この考え方に基づけば、企業は製品を通じて顧客と「価値を共創する」立場にあり、価値の主体は顧客にあることが明確になります。
G-DロジックとS-Dロジックの比較
| 項目 | G-Dロジック | S-Dロジック |
|---|---|---|
| フォーカス | 製品の生産・販売 | サービスと体験 |
| 価値の源泉 | 品質、価格、機能 | 使用文脈、顧客体験 |
| 顧客との関係性 | 取引中心 | 長期的な共創関係 |
| 価値の提供方法 | 一方的な提供 | 双方向的な創出 |
| 顧客の役割 | 受け手 | 共創者 |
シャンプーを例にした価値の捉え方
- 機能的価値:汚れを落とす、フケを抑える、泡立ちが良い
- 情緒的価値:ボトルのデザイン、使った時の心地よさ
- 自己実現価値:購入による社会貢献など
いずれも「モノをお金と交換する」ことを前提としていますが、S-Dロジックはその枠を超えて顧客との関係性を見直します。
文脈価値とは何か
文脈価値とは、顧客が商品やサービスを「自分の生活の中でどう使うか」によって感じる価値です。
企業は価値を提供するのではなく、顧客の価値創出を支援する立場となります。
価値は共創される
価値は、企業と顧客が持つ文脈の出会いによって創出されます。つまり、企業が一方的に価値を提供する時代は終わりを迎えつつあるのです。
マーケティングのあり方も、顧客との関係性を軸とした共創型へと変化しています。
こらぼたうんの実践
当社 こらぼたうん は、2001年の創業以来、企業と生活者の共創に取り組んできました。
商品は購入時ではなく使用・体験の中で価値が生まれることを踏まえたマーケティング支援を実施しています。
文脈価値を高める3つの視点
- 顧客の生活文脈を深く理解する
- 商品が使われる背景と目的を探る
- 顧客との対話を通じて価値創出に取り組む
まとめ
文脈価値と価値共創の考え方は、単なる商品差別化ではなく、顧客との長期的な関係構築を可能にします。
製品やサービスが「どのように使われるか」に注目し、顧客との共創によって持続可能な競争優位を築くことが、これからのマーケティングの本質です。